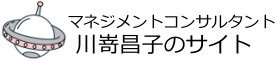「人生最大の怒り」に関して思うこと

スケールテクニック
アンガーマネジメントの手法に「スケールテクニック(怒りの温度計)」というのがあります。
これは、自分のその時々の怒りの度合いを0から10の数値で表わすものです。0が「穏やかな状態」、10が「人生最大の怒り」です。
「スケールテクニック」は、怒りを可視化することで、客観視でき、冷静になれるというメリットがあります。また、自分がどんなことでどれくらいの怒りを感じやすいか分かるため、対策が取りやすくなります。
この「人生最大の怒り」に関して、ある記事とある番組を見て思うことがありました。
CNN特派員が感じたショック
記事は、イスラエルの中道左派の新聞「ハアレツ」に、6月21日に掲載されていた「CNNの戦争記者として、アルワ・デイモンはあらゆるものを見てきたと思っていた。そしてガザへ向かった」です。
デイモン氏は、CNNの上級国際特派員として、2003年から、中東の紛争地帯をずっと取材してきています。軍とともに戦地に赴き、危険な目に遭い、ジャーナリストの仲間や人道支援活動家の親友が殺されたりもしています。
そのため、「死、破壊、難民化、人道的危機……それらは、私たちが戦争の現実の一部として受け入れることに慣れているものです」という状態でしたが、ガザでは、ショックを受けたと言います。
たとえば、ガザのある女性は、7歳の息子のことを心配していました。息子は毎晩叫ぶからです。それは、妹(女性の娘)の首が吹き飛ぶのを見たからです。
その女性は、それを話すときに、まったく感情を表に出しませんでした。その女性も、娘の惨事に居合わせたにも関わらず。少しでも感情を出すと「彼女は粉々に砕け散ってしまうからです」と、デイモン氏は言っています。
その女性は、デイモン氏に対して、「ええ、わかっています。でも、私には私を必要とする生きた子どもたちもいるんです」と言いました。
ガザには、そういう、感情を殺して生きている人たちがあふれていることに、デイモン氏はショックを受けたのです。
被爆者が語ったこと
番組は、先日、友人の友人が、ギャラクシー賞を受賞した「ながさき原爆記録全集 山端庸介原爆全写真 被爆翌日117枚全解析」で、これに出てくる被爆者のインタビューが興味深いです。
その被爆者は、四田シズヨさんで、息子(乳児)が泣くため、防空壕に移動。そのときに被爆しました。翌朝、自宅に戻ろうとしますが、一帯は瓦礫と化し、たたずむ姿を、気づかないうちに写真に撮られていました。
四田さんはなんとか自宅(の残骸の場所)に戻り、父親と夫、姪、3人の遺骨を拾いました。
四田さんは「人間の感情て、なかとね、あの当時はね」「一番のつらかときは、人間の感情は出んよ。涙も出ん」「そのときはとにかくなんも感情はなかとね。怖かも、熱かも、なんもね。悲しかも、嬉しかも全然分からんやったでしょう」と語ります。
感情停止
ガザの女性も、被爆後の長崎の四田さんも、街が破壊され、家族が変わり果てた姿になったとき、恐らく「人生最大の怒り」を感じたであろうに、「怒り」だけでなく、すべての感情が停止しています。
この「停止状態」は、動作も停止する「フリーズ(固まる)」状態とは違い、動作は止まっていません。
2人とも、小さな子どもを抱えており、生き延びるために、感情が止まってしまったのでしょう。
四田さんは、やがて感情は戻り、原爆で夫を失ったことに「もう歯がゆかごたっですよ」と、歯がゆさ、悔しさを募らせていました。
ガザではまだ戦闘が続いているため、先の女性は、生き延びるためにまだ無感情かもしれません。
「人生最大の怒り」を「無感情」にしてしまうほどの出来事、戦争は、天災ではなく人災、人によるものなので、「行なわない」という選択肢もあるはずなのに、なくなりません。
とくに、今回のガザの戦闘において、デイモン氏は、これまでとは違う「最も恐ろしい経験」をしていると言います。
戦争でも、事前に伝えている人道支援団体、とくにイスラエルの友好国であるアメリカや西側諸国のメンバーは、安全の保障が得られるというルールが機能していないことや、他の紛争地域とは違って、ガザの人々は「地獄」に閉じ込められていることについて語っています。
現在の日本のように平和な国に住む人が、おそらく生涯感じることがあるかないかぐらいの「人生最大の怒り」を、戦争は、多くの人の「不幸」とともに簡単に生みだします。
軍事産業や各国の思惑など、いろいろな課題はあっても、「知恵」でヒト属として唯一生き残ってきた「ホモ・サピエンス」の我々としては、「結局、戦争で滅びちゃったね」とならないようにするべきでしょう。