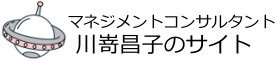「長崎―閃光の影で―」が伝えるもの

結婚、出産、家族写真――すべてが消える「明日」
この映画は、パンフレットによれば、映画「TOMORROW 明日」に続く位置づけとのことです。
「TOMORROW 明日」は1988年8月に公開された作品で、長崎原爆投下の1日前、1945年8月8日の長崎が舞台です。ささやかな結婚式が行なわれ、花嫁の姉は陣痛が起き、翌朝(8月9日)、子どもが生まれます。登場人物たちは、あれこれ悩んだりしながらも一生懸命生きています。基本的には、私たちと変わらない、どこにでもいる普通の人たちの、ある意味、ありふれた日常のひとこまです。
「明日」という言葉に対して、私たちは、明るい未来をイメージすることが多いと思いますが、この映画の「明日」は、原爆が投下され、ささやかな日常も、町も命も吹き飛んでしまいます。
映画の花嫁(ヤエ、看護師)やその姉、生まれたばかりの子供や家族はどうなったのか、分かりません。
この映画が公開された1988年、私は東京にいて、5月に結婚しました。
この映画を見て、何かに感想を書いた覚えがあります。
原爆投下前の町の写真、学校の集合写真や家族写真は、長崎原爆資料館、広島平和祈念資料館に展示されていて、写真を撮ったときには確かに存在していた風景や、元気にしていた人たちが、原爆で、一瞬で失われてしまったことが、別の写真、映像で分かります。
私たちが普通に続くと思っている「明日」が、町ごと、家族や友人も吹き飛び、たとえ生き延びても、過酷な状態になるのが、戦争でもあります。
帰郷していた看護学生たちの「明日」から後
「TOMORROW 明日」の1945年8月9日以降の長崎の様子の映画が、今回の「長崎-閃光の影で-」です。
けれども、「TOMORROW 明日」の登場人物とはつながっていません。ヤエさんという看護師が登場しますが、顔が違うので別人でしょう。「TOMORROW 明日」のヤエさん役の南果歩さんは、違う役で登場しています。
「長崎-閃光の影で-」は、長崎に原爆が投下された時の、看護学生3人を主人公とする話です。1980年に日本赤十字社長崎県支部が編纂した証言集「閃光の影で―原爆被爆者救護 赤十字看護婦の手記―」をもとにしています。
看護学生たちは、大阪の看護学校に通っており、空襲で休校になり、長崎に帰郷していました。パンフレットには、1人(田中スミ)は17歳と書いてあり、残りの2人の年齢は書いてありませんが、同じぐらいか、原爆の証言で、当時の看護学生で、14歳、15歳の方もいらっしゃるので、それくらいかもしれません(映画のなかで、1人は14歳と言っていたような?)。
8月9日の朝、スミは島原の愛野にある祖母の家へバスで向かい、他の1人(岩永ミサヲ)はカトリックで、父と浦上天主堂に行き帰る途中で、もう1人(大野アツ子)は日赤長崎支部で働いていました。
パンフレットによると、当時、日赤長崎支部は、今の諏訪町にあり、ここは爆心地から3.2キロ離れています。けれども、ガラス(窓、薬品ケース、書棚)は全部割れたと、証言(長崎東高在京同窓会)に書いてあります。証言では、現在の長崎大学経済学部、長崎市立図書館(旧 新興善小学校)、勝山、銭座、磨屋などに救護所が設けられたようです。
長崎の原爆は、当初、「常盤橋」(眼鏡橋より2個、浜町寄りの橋)が目標だったようで、このあたりは、江戸時代から続く商店街、繁華街であり、日赤長崎支部もそこにあったため、そこに投下されていれば消えています。
たとえ神様は許しても
原爆は、浦上天主堂や長崎大学医学部(当時は長崎医科大学)の近くに落とされ、当時、日本最大のキリスト教徒の町だった浦上は、信者の3分の2以上が亡くなっています。東洋一の教会、浦上天主堂が、(目立つので)投下の目標となったという説もあり、江戸時代のキリスト教弾圧に耐えてきた信者たちは、皮肉なことに(プロテスタントとカトリックの違いはありますが)キリスト教の信者が多いアメリカにより、壊滅してしまったのです。
映画で、キリスト教の神様はこれ(原爆投下)も許すのかということを言って、言い争いになるシーンがありましたが、私は、神様はどうか知らないけれども、人間は許しちゃダメだろうと思いました。
核兵器は非人道的な兵器であり(そもそも兵器は全部非人道的ですが)、投下したらどうなるかは研究され分かっていたし、投下の必要もなかったからです。 ここでは詳しく書きませんが、「米国の指導者たちは原爆を投下する必要はないと知っていた」というロサンゼルス・タイムズの記事もあります。
この映画でも、原爆投下の際には無傷で元気だった人が、放射能の影響で、しばらくすると亡くなるということが起きています。
私たちの明日を不幸にしないために
看護学生たちは、まだ学生なので一人前ではなく、怒られたりしながらも救護に尽力するのですが、運ばれてくる人たちは悲惨で、どんどん亡くなっていきます。
映画のパンフレットに、「原爆の恐ろしさをどこまで再現すべきか」ということで、「実際の様子をカラーで再現すると、正視に耐えられない観客も多いと考え、多くの方に見てもらえることを優先しました」と書いてあります。
つまり、実際は再現できないほどの惨状だったのです。
ただしキャスト向けには、ドキュメンタリーを鑑賞したり、原案の手記を朗読したりのワークショップを行ない、現場の臭い、人肉が腐敗する異臭や垂れ流しの汚物の悪臭に近い「くさや」を嗅いでもらったとのことです。
私が子どもの時は、戦後30年ぐらいで、10代で被曝した人は40代です。
原爆投下や戦争が風化してしまうことに危機感をもった大人、先生も多く、何も知らない子どもたちに事実を伝えなければと、力が入っていました。
そのため、被曝者本人たちから、理不尽で恐ろしい体験が、多少は配慮があり、伝える限界はあるとしても、基本的には直接、ストレートに伝えられました。
今は、もはや戦後80年で、当時の体験を語れる人はほとんどおらず、戦争を知らない世代が、3~4世代目になり、完全に「歴史」になっています。映像、証言集、展示はあっても、理不尽さ、恐怖、痛みまで伝えるのは難しいかもしれません。
しかし、それでも、何が起きたのかという事実と、当時の人たちの声を伝えていく必要はあります。イメージできないと、歴史は繰り返し、「明日」が吹き飛ぶので。
パンフレットにも「本作が戦後80年の夏で終わってしまうのではなく、原爆の語り部となって長く多くの方に届いてほしいと願っています。(略)ぜひともいろんな方に伝えていただけたらと思っています」とあります。
今、市民生活の中で、暴力、殺人、放火などは犯罪であり、許されないものとなっています。そして、争いが起きて、話し合いでは解決しない場合、裁判で、法に基づいて決着することになっています。
それを国際的にも目指すのを決してあきらめてはいけないと思います。
暴力、殺人、放火の大規模なものである戦争は、人を不幸にします。核戦争は、人類滅亡にもつながります。知恵で生き延びてきたホモサピエンスの我々が、阻止できないわけがないと信じたいです。
追記)エンドロールの「取材協力」に友人の友人、吉村文庫さんの名前があったので、おっ!と思いました。吉村さんは、長崎の原爆を伝えることにめちゃくちゃ力が入っていて、ギャラクシー賞もとっています