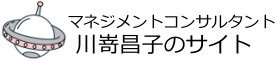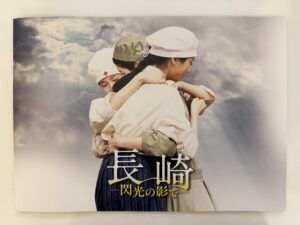パレスチナの歴史~この80年

8月8日に、長崎市で、市民団体(パレスチナと長崎をつなぐ会)による「戦後80年:パレスチナ大使から長崎に伝えたいこと」という講演会が行なわれます。このイベントでは「激動の歴史を歩んできたパレスチナの80年」についても学ぶ内容になっています。
そこで、私も、パレスチナのこの80年の歴史に関してまとめました。
今年は、日本にとっては、「戦後」80年ですが、パレスチナにとっては、ずっと「戦中」80年です。
今のパレスチナの状況、すなわちガザの9割以上の建物が破壊され、死者数が6万人を超え、飢餓が拡大している状態は、直接のきっかけは一昨年10月のハマスによる攻撃ですが、その発端になっているのは、じつは78年前の出来事です。
今に至る「パレスチナの歴史」をまとめました。
今から80年前、1945年のパレスチナ
イギリスの委任統治領……第一次世界大戦で、オスマン帝国が滅亡したため、1922年から1948年まで、パレスチナはイギリスの「国際連盟による委任統治領」として統治されていました。
ユダヤ人とアラブ人の対立が激化……ユダヤ人は、古代ローマ、中世ヨーロッパ、近世・近代ヨーロッパと迫害されてきましたが、1896年にテオドール・ヘルツルが提唱した「シオニズム」(パレスチナにユダヤ人の国をつくる)により、パレスチナにユダヤ人が移住。第二次世界大戦後、ヨーロッパからナチスの迫害を逃れたユダヤ人が多数流入し、アラブ系住民との対立が深まっていました。
ユダヤ人の人口割合は約30%……1945年時点で、パレスチナには約200万人が住んでおり、そのうち約30%がユダヤ人、70%がアラブ人(主にムスリム、一部キリスト教徒)でした。
1947年 国連が「パレスチナ分割決議」を採択
イギリスが、パレスチナ統治を放棄すると表明したため、国連がパレスチナの土地を分割し、イスラエルとパレスチナの2国を作ることを11月29日に決議しました(決議181)。
ただし、ユダヤ国家が55%の土地、アラブ国家が45%の土地、エルサレムは聖地なので国際管理地域としたため、ユダヤ側はこれを支持しましたが、アラブ側は「自分たちが多数派(70%)なのに、土地が狭いのはおかしい」と反対しました。
1948年 イスラエル建国、ナクバ、第一次中東戦争
イギリスのパレスチナ統治が終了する前日の5月14日、ユダヤ人指導者、ダヴィド・ベン=グリオンが、イスラエル国の独立を宣言。
5月15日は、イスラエルにとっては建国の翌日ですが、多数のパレスチナ人が、イスラエルの武力により土地を追われたため、パレスチナ人にとっては「ナクバ(大災厄)」の日となっています。
同日、周辺のアラブ諸国が軍事介入し、第一次中東戦争が起きましたが、イスラエルが勝利し、分割案以上の土地を実行支配することとなりました。
パレスチナ人の数百の村が占領、破壊され、75万人のパレスチナ人が難民になりました。
国連は、「難民の帰還・補償を求める決議」(決議194)を出し、難民には帰還の権利があり、帰還させるか、帰還を望まない者には補償をするようにということが決まりました。イスラエルはこれを拒否し、国連パレスチナ調停官(フォルケ・ベルナドッテ。スウェーデン人)は、イスラエル過激派により殺害されました。
現在に至るまで、パレスチナ側は、この決議にもとづく帰還を求め、イスラエル側は拒否しています。
パレスチナ難民は、国連パレスチナ難民救済機関(UNRWA)によれば、2024年時点で、約590万人以上となっています。ヨルダンにはこのうち230万人がいて、10の難民キャンプがあります。
1967年 第三次中東戦争(六日戦争)
アラブ諸国で、軍事同盟の動きがあったことなどにより、イスラエルが「自衛のための先制攻撃」を実施。イスラエル空軍が、エジプト空軍の基地を奇襲攻撃し、シリア、ヨルダンの戦闘に拡大しますが、わずか6日で、イスラエルが圧勝します。
その結果、エジプトが管理していたガザ地区、ヨルダンが管理していたヨルダン川西岸、東エルサレム、シリアが管理していたゴラン高原をイスラエルが占領します。
国連は、イスラエルに占領状態の継続は違法として、占領地からの撤退を求めますが、拒否。パレスチナ人の土地はさらに縮小し、イスラエルの占領統治と入植が拡大しながら今に至っています。
1987年 第一次インティファーダ(民衆蜂起)
パレスチナ住民の大規模な抵抗運動(非武装の草の根運動)が始まり、国際的にも注目されます。
1967年以降、ガザ、西岸、東エルサレムが、イスラエルに占領され、パレスチナ人は、土地や財産の没収、移動制限、検問、差別などに直面していました。
1987年にガザで、イスラエル軍事車両がパレスチナ人を死亡させる事故が引き金となり、抵抗運動が始まりました。
具体的には、イスラエル兵や戦車に向かって石を投げる、壁に「自由」などのスローガンや絵を描く、ゼネストなどでしたが、イスラエル軍は軍事的手段で鎮圧し、多数の死傷者が出ました。
石を投げる子どもをイスラエル兵がライフルで撃つなどして、イスラエルは国際的に非難されたりもしましたが、イスラエルは「自衛の権利がある」と主張しています。
1988年 パレスチナ独立宣言
PLO(パレスチナ解放機構)議長、ヤーセル・アラファトが宣言し、1988年末までに約90カ国が承認。現在は140カ国以上が承認。イスラエルと、アメリカ、日本などG7は認めていません。現在、フランス、イギリス、カナダは検討中。
1993年 オスロ合意(パレスチナ暫定自治)
イスラエルとPLOが相互承認し、共存の第一歩としますが、難民帰還、東エルサレムの地位、占領、入植地などにおける合意が出来ませんでした。
イスラエルは、占領、入植、検問、拘束、通行制限を続け、自治は名ばかりで、経済、インフラ、移動はイスラエルが握ったままでした。
パレスチナはこれに対抗し、自爆攻撃を行ないます。
そして、オスロ合意に反対した極右ユダヤ人により、イスラエルのラビン首相が暗殺されます。
2000年 第二次インティファーダ
独立宣言しても、イスラエルの支配は続き、和平交渉は行き詰まったことから、再び抵抗運動が起きます。投石、デモ(非武装)に加え、自爆テロ、ロケット弾(武装)の攻撃が加わりました。
2005年 イスラエルがガザから撤退
イスラエルは、ガザ地区にあったユダヤ人入植地と軍施設を撤去し、撤退(パレスチナとの交渉はなく、一方的に撤退。返還はしていない)します。
2006年 ハマス政権
ハマスが選挙で勝利し、第一党となり政権を握ります。
この選挙は、国際監視のもとで行なわれ、公正な民主選挙と認められましたが、イスラエル、アメリカは、ハマスをテロ組織と指定し、政権を承認していません。
イスラエルがハマスを認めていない理由は、ハマスがイスラエル国家の存在を認めていないこと、イスラエルへのロケット攻撃やテロ行為、イランとのつながりを脅威とみなしていることなどです。
イスラエルは、ハマス政権への政治的活動の妨害を宣言し、実際にさまざまな妨害、資金差し押さえや政治家の拉致などを行なっています。
そのため、ハマスは第一党(日本では自民党の立場と同じ)にもかからわず、日本でも「イスラム組織 ハマス」と報道されています。
ガザと西岸の分裂……ガザ地区ではハマスが支配、西岸はファタハ(PLOの主要な政党)が支配し、パレスチナ内で分裂状態になっています。
2007年 イスラエルが、ガザを封鎖
イスラエルが、ガザを封鎖し、厳しく監視する体制を敷きます。
具体的には、検問所を設け、人の出入り、物資の搬入、輸出入などは、国連やNGOでも、イスラエルの検問、許可が必要。病人や留学生でも拒否される場合があります。
インフラ(電力、水道、燃料、通信)もすべてイスラエル経由で、制限、停止されます。海と空も管理下に置かれています。
国連や国際機関は、「国際人道法上、禁止されている行為」としていますが、今に至るまで継続されています。
2008年以降 イスラエルとガザの間で、頻繁に軍事衝突
ハマスは、イスラエルによる占領に対抗し、ロケット弾での攻撃を実施。
イスラエルは、「自衛」として、ガザを大規模空爆、地上侵攻。その度に、パレスチナの民間人が多数死亡しています。
2018~2019年 帰還大行進
ガザ住民が、国境フェンスに近づく大規模デモ(非武装)を行ない、イスラエル軍が狙撃。非武装のデモに死傷者が多数出たことで、イスラエルは国際的に非難されますが、「自衛」と主張。
2023年 ハマスによる越境攻撃
これまでは、ハマスがイスラエルにロケット弾を撃ち、迎撃され、ガザが空爆、地上侵攻されていましたが、越境攻撃を行なったため、イスラエルが全面報復。
これまでも、イスラエルは学校や病院、国際機関への攻撃を行なってきましたが、規模が大きく人道危機が深刻化していることで、国際社会からの目が集まっています。
なぜイスラエルは国連決議に従わなくてもいいのか?
イスラエルは、建国は、国連決議を根拠としていますが、それ以外は、国連決議を一切無視しています。
国連の多くの決議には、そもそも法的拘束力はありません。しかしながら、国際的な信頼、倫理的責任、外交や経済への影響を鑑み、多くの国は守ることを選択しています。
さらに、より強い効力をもつ安全保障理事会決議では、アメリカが拒否権を使うことで、イスラエルへの制裁がブロックされます。つまり、アメリカが盾になっている状態です。
なぜアメリカがイスラエルを支持するのか?
絶大な影響力をもつユダヤ系アメリカ人……アメリカには、1880年代から1945年以降まで、迫害から逃れて来たユダヤ系の人たちがいて、政財界、メディア、学術などさまざまな分野で重要な役割を果たし、アメリカのイスラエル政策に影響を及ぼしています。
とくに、政治においては、強い影響力をもつロビー団体、AIPAC(アメリカ・イスラエル公共問題委員会)の存在があります。
上院、下院の議員ほぼ全員(党派によらず)と接点をもち、絶大な影響力をもち、歴代の大統領はイスラエルに配慮した政策をとってきました。メディアとも結びついており、世論という面でも、イスラエルを支持しないことによる政治的リスクはきわめて高いと認識している議員が多数派です。2022年からは、政治資金団体として、選挙への資金介入が本格化しています。
ただし、ユダヤ系の人々が、皆、現在のイスラエル右派政権を支持しているわけではなく、イスラエル支持は掲げながらも、リベラルな立場で、パレスチナとの共存を目指す「J Street」というイスラエル支持団体もあります。
中東での戦略的パートナー……アメリカにとって、中東は、石油や地政学的影響力において重要です。アラブ諸国が不安定でロシア寄りに対し、イスラエルは安定的で西側寄りと捉えています。
キリスト教福音派……旧約聖書に、神がユダヤの民を再び土地に戻す記載があり、福音派(福音派プロテスタント)は、イスラエルの建国、存続は「神の意思」と捉えるのに対し、カトリック、メインライン・プロテスタント等は、現代の政治とは結び付けず、中立的に捉えています。
アメリカ成人におけるキリスト教徒の割合(2023-24年)は62%で、福音派が23%、メインライン・プロテスタントが11%、カトリックが19%、その他が9%となっています。
すなわち、アメリカ人の成人の約4分の1が福音派です。
トランプ大統領は、その他に入る長老派であり、熱心なクリスチャンではないと言われています。
しかし、トランプ大統領の福音派からの指示は高く、その理由は、中絶反対、同性婚反対などへの共鳴ですが、支持者である福音派を尊重しないわけにはいきません。
イスラエルの「自衛」の考え方
第二次世界大戦後の日本は、直接の戦争リスクが低い状態が続いているため、「自衛」は「専守防衛」(攻撃されてから対応。必要最小限)、「憲法上の制限付き抑止力」ということになっています。
これに対して、イスラエルは、建国からずっと戦争を続けており、先制攻撃を含む「積極防衛」です。
イスラエルは建国前から、武装組織を作り、軍人経験者を収集し、軍事訓練を行ない、武器の入手(密輸も含む)、テロ活動、強力な軍事組織を作り上げています。
建国後も、「武力をもたなければ滅ぼされる」「国民皆が兵士(女性にも兵役がある)」というポリシーのもと、武力強化を図っています。
先制攻撃は、国際法では、敵がまさに攻撃しようとしている場合に限っており、動きがないのに攻撃する「予防戦争」は国際法違反です。しかしながら、イスラエルにとっては、将来的に敵となる可能性が感じられれば、完全に芽を摘んでおくのが「自衛」です。
アメリカは最初は慎重でしたが、政治におけるユダヤ系の強大な影響下、支援を続けています。
このような状況下、パレスチナにとっての明るい兆しは?
フランス、カナダ、オーストラリア、イギリスなどが、パレスチナ国家の承認に前向きな発言をしています。
この理由は、国際的に、人道的見地からイスラエル現政権への批判が集まっている流れを受けたものです。
各国の国内世論が「イスラエルの軍事行動は行き過ぎ」となり、「アメリカ追従を続けると、世論の反発で政権を失うリスクがある」という危機感から、外交姿勢を見直しはじめている側面があります。
私たち日本の市民が出来ることは、歴史の事実を知る、まわりの人にも伝える、現在の動きを知ること。
そして、平和や人権について、政治や宗教、民族を超えて、地球人として、人間として、自分たちがその(パレスチナ人の)立場ならどうなのかを考えること。
そして、選挙で政治家を選ぶ際に、あるいは、買い物などで企業を選ぶ際に、それを考慮した選択をすることだと思います。