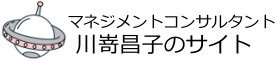『さらば、自民党』が示す日本の現在地
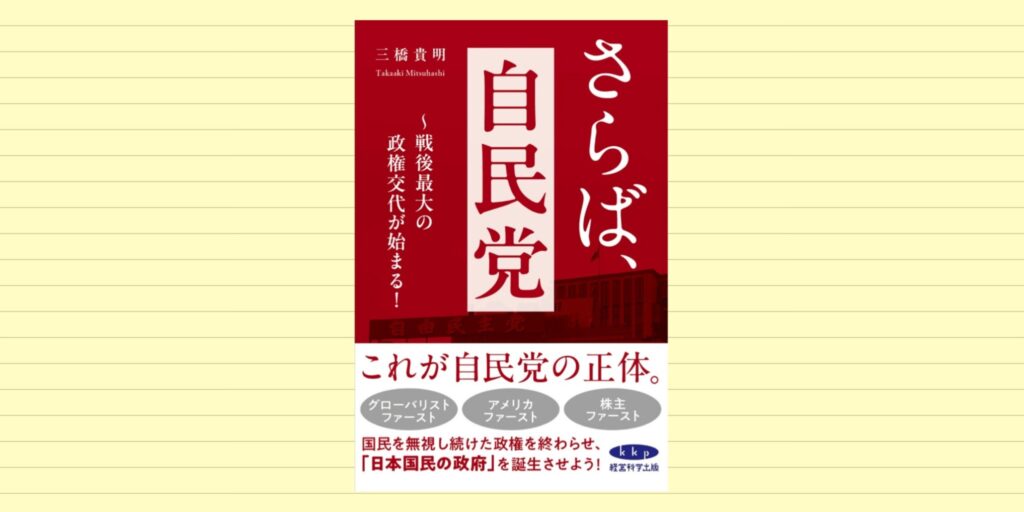
正論なのに知られていなかったこと
三橋貴明氏の著書『さらば、自民党』を読んだ感想を書きます。
じつは、まだ書籍は届いていなくて(今、輸送中になっています)、先に読める電子版で、全部読んでしまいました。
私は『月刊三橋』を定期購読し、三橋貴明氏の講義や時事分析を日頃から聞いています。この『さらば、自民党』の内容も、これまでに触れられてきたテーマですが、1冊にコンパクトにまとめられ、わかりやすいのでおすすめです。
三橋氏がこれまで語ってきたことは、正論、すなわち経済学的には常識、歴史や統計的に見ても正しい、国民目線で考えれば当然のことばかりですが、世の中的には、あまり理解されていなかった。というよりも、知られてもいなかったかもしれません。
大企業や外資の都合で真逆の考えが「常識」として刷り込まれてきた
たとえば、“正論”は、下記のようなことです。
- 消費税は景気を冷やし、企業も家計も疲弊させる(企業の負担増で賃金や雇用が縮み、家計を圧迫するため)
- デフレ下では財政拡大が必要(民間が支出を減らしている時は、政府が需要を補う必要がある)
- 民営化は国民の負担を増やし、公共サービスが切り捨てられる危険性が高い(公共サービスが利潤優先になり、料金上昇、サービス低下、海外資本による買収が進むとともに、赤字地域、赤字サービスが切り捨てられるため)
- グローバリズムは国民経済を解体する(国内産業と雇用が海外資本に吸い上げられる)
- 国債は「国民の借金」ではなく「国民の資産」(政府の負債は民間の金融資産として保有されるため)
- 移民政策は人手不足解消よりも低賃金化を招く(人員が一時的に増えても、待遇改善や生産性向上につながらず離職率も高いため、人手不足は解消せず、結果的に賃金水準が下がるだけ)
こうした主張は、テレビ、新聞、財務省、一部の学者によって、真逆の考えが「常識」として刷り込まれてきました。いまだに、発言力のあるインフルエンサーたちが、堂々と正論を否定する発言をしています。
それには当然、理由があります。
たとえば、消費税の導入・増税の背景には経団連の要請があり、「輸出還付金」という仕組みで大企業が利益を得ています。輸出企業は消費税を負担せず、むしろ“補助金”のように受け取ることができるのです。その穴埋めを、中小企業と一般消費者が担わされています。
大企業や外資を潤わせ、そこからの献金、資金提供を頼りにする自民党という構図があるのです。
結果として、増税、緊縮財政、民営化、規制緩和、外資優遇といった政策が(マスコミを使ったプロパガンダもあり)“改革”として歓迎され、一方で国民生活はじわじわと貧困化し、家計も中小企業も地域も疲弊していく――そんな30年が続いてきたわけです。
これまでの構造と背景がまとめられている
『さらば、自民党』では、その構造と背景を、次のような切り口で整理しています。
- 戦後の対米従属(日本の主権や外交・軍事判断をアメリカに握られてきた構造)
- 財務省と経団連の利害(増税・緊縮財政・外資優遇などで国民より大企業の利益を優先)
- 小選挙区制と政党助成金(党本部が議員を支配し、民意より党利が優先される仕組み)
- 官僚統制とグローバリズム(国民の生活より規制緩和・市場開放・外資の意向が優先)
- 若者の政治離れと転換点(“既存政党への拒否”から新勢力へ支持が移動)
この本は、自民党批判ではなく、むしろ、これまでの歴史的経緯と、今、ようやく国民が、これまでの事実と語られてきた嘘に気づき始めた転換点にあることを示しているものでした。
若者の投票行動や、参政党・国民民主・れいわなどの台頭は、これまでの「政治にはまったく期待できない」「どうせ何も変わらない」という諦めの空気が変わり始めたことを象徴していると思います。
『さらば自民党』は、今後、国民が政治を取り戻すための入り口になるはずです。