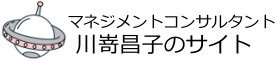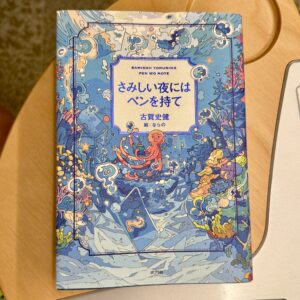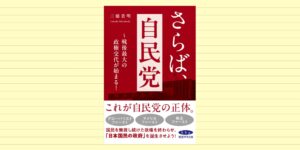“無力”と言われてきた私たちは、SNS時代に何ができるのか?

触れない、関わらないのが普通だった
「政治の話は避けたほうがいい」
「国際問題には触れないほうが無難。宗教などが関係していて面倒」
こうした言葉を、学校や職場、何らかの集まりで耳にすることは少なくありません。
そして、「政治や国際問題は、自分たちとは無関係」と、興味をもたない故に、知らない、考えない、関わらないことが普通という空気になっていたかもしれません。
調査報告「アジア10カ国の若い世代の政治に対する認識と関与(2023年)」でも、自国への政治に比較的関心が低く、政治に対してよくわからない、話題にすることもないという日本の若者の(おそらく若者だけではない)傾向が現われています。
この「政治、国際問題はタブー」の空気のため、国の方針、国際問題などに関して、何らかの“納得できないこと”が浮上してきても、「自分ひとりじゃ何も変わらない」「一市民にできることはない」と、無力感を感じる結果になっているのかもしれません。
しかし、本当に、私たちは「何もできない存在」なのでしょうか?
マスコミ報道に頼るしかなかった時代からSNSの時代へ
かつて、私たちに届く情報は、テレビや新聞、いわゆるマスコミ報道がほとんどでした。
どの話題を、どのように取り上げるかは、限られた機関に委ねられていて、私たちは「知らされる側」にいるしかありませんでした。
ときには、大事な出来事が報じられず、「知らないまま」だったり、プロパガンダ(政治的な宣伝)にもとづいた情報を鵜呑みにし、踊らされたりすることもあったのではないでしょうか?
しかし、今は、SNSで、マスコミが報じないことが情報として上がってきたり、拡散されたりもしています。かつては届かなかった現場の事実、当事者の生の声が、国境も立場も越えて届くようになりました。
もちろん、SNSの情報は玉石混交です。
人気のYouTubeチャンネルで、視聴者がおそらく気づいていないであろうタイアップ企画もあります。すなわち、ある企業や団体、国の意向が反映され、新たなプロパガンダになっていたりもするわけです。
それでも、マスコミ以外の情報が得られるようになったという事実、「知らないままでいる」ことから、「知ったうえで選ぶ」ことができるようになったのは、大きな変化ではないでしょうか。
SNSが開いたもうひとつの変化
そして、「知る」ことにより見逃せない変化が起こりつつあります。
それは、私たち一人ひとりの選択の影響です。
昨今の選挙では、若い世代の投票行動が既存政党の勢力を大きく変えました。
これまで「政治に無関心」と言われてきた層が動いたことで、勢力図が変わりつつあります。「どうせ変わらない」と思っていたものが、実際に変わってきたのです。
ただし、その背景には、長く続いてきた“意図的な無力化”の構造もあります。
国民の投票や判断には本来、大きな力があるにもかかわらず、
- 自分ひとりでは何も変わらない
- 知ってもどうしようもない
- 政治は触れると面倒
そう思わせておいたほうが、権力側には都合がよいのです。
戦後教育では「政治は専門家に任せるもの」「市民が口を出す領域ではない」という考えが刷り込まれてきました。
また、学生運動や労働争議などの歴史的背景から、「波風を立てないほうが安全」「反体制だと思われると厄介なことになる」という空気も残っていました。
しかし今、私たちはその“沈黙の前提”から少しずつ抜け出し、自分たちの「動かす力」に気づき始めています。
では、私たちは、この時代に何をしたらよいのでしょうか?
まず「見抜く」ことから始まる
情報が溢れすぎている時代、私たちは、玉石混交の情報から何を拾うかが問われる状況にいます。最初の一歩は、情報を「見抜くこと」です。
たとえば、
- 誰が発信しているのか
- 一次情報か。もしくは、出典や一次情報をたどることができるか(根拠があるか)
- 類似の情報はあるか
- 何を目的に伝えられていると思われるか
- その情報で誰が得すると思われるか
- 反対の立場から語る情報はあるか
- 感情を煽る内容になっていないか
- 怪しい点はないか
こうした視点を持つことで、情報に振り回されるのではなく、主体的に選び取る側に立つことができるでしょう。
小さな選択が社会を動かす力になる
そして、知ったことを何らかの選択、行動につなげる、といっても、大きなことをする必要はありません。
たとえば、
- 信頼できる情報源(YouTube、SNS、専門機関、マスコミ情報等)を複数もつ
- 不当な出来事に疑問をもち、関連情報を調べる
- 関心の出てきたことに関する本を何冊か図書館で探して読む、あるいは講演会などやっていたら参加する
- 誰かの意見を頭ごなしに否定せず、その背景(なぜその人がそう考えるのか)に関心を寄せる
- 信頼できる情報はSNSで共有する
- 選挙に行く
- 寄付や署名、メッセージなど、できる範囲で意思表示をする
知る → 選ぶ → 伝える → 関わる
これを行なうことで、“無力”という思い込みから抜け出すことが可能でしょう。
そして、これこそが、私たちがSNS時代に手にした「静かな力」なのではないでしょうか。
私たちはこれまで、自分を社会的には「何もできない」と思ってきたかもしれません。けれども、何かを変える力は、遠くの誰かではなく、私たちの日々の小さな選択の中にすでに芽生えています。
SNS時代に生きる私たちは、「知らないままにしておくこと」も、「見て見ぬふりをすること」も選択肢のひとつです。
けれども、それを一歩だけ越えてみたら、私たちの影響力は、想像よりずっと大きいのかもしれません。