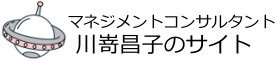「反省」というより、何を学び、今どう活かすかが大事

石破首相は全国戦没者追悼式で、太平洋戦争に対して「反省と教訓を、今改めて深く胸に刻まねばなりません」と発言しました。
普通、反省は自分の言動に対して行なうものであり、80年後の私たちが、現在の状況、価値観で、当時の日本政府の判断、行動をジャッジすることに違和感があります。そして、義(正しさ)を信じて、日本の国や家族を守るために戦った人たちや、犠牲になった人たちにとっては、「未来の人(=今の私たち=子孫)」に「反省」されても憤りを感じるだけでしょう。
そのうえで、あえて振り返るのなら、重要なのはそこから何を学び、今や未来にどう活かすのかという点だと感じます。つまり、太平洋戦争について、「今に置き換えると、どんなヒントが得られるか」という視点が欠かせないと思います。
戦略なき行動の危うさ
太平洋戦争を仕掛けたのは、長い準備を経たアメリカでした。1846年頃から「日本を軍事的影響下に置く」ことを視野に入れ、緻密に練られた「オレンジ計画」に基づいて戦争を始めています。
日本は陥れられたのであり、いろいろな挑発をしてもなかなか乗ってこない日本に対して、アメリカは戦わざるを得ないように追い詰めていったのです。けれども、あえて日本政府の「落ち度」ということで書くと、自らを過信し、希望的観測に基づいて動き、逆転を狙った結果、必要以上のダメージを被ることになったことです。
もっともアメリカにとっては、他国を「陥れること」も戦略の一つで、自らの目的のためには手段を選ばないという考え方です。
そのため、たとえるなら、目標を明確にし、戦略を立て、計画通り努力してきた受験生(アメリカ)に対し、「なんとかなるだろう」と準備不足で挑んだ受験生(日本)のようなものです。結果は惨敗。その後の日本は、敗戦国としてアメリカから数々の無理難題を突き付けられ続けています。
今後に必要なこと
そして今も世界には、長期的な戦略に基づき、他国を支配下に置こうとしている国や、理不尽な要求をする国、武力行使をためらわない国が存在します。
だからこそ、日本は「何に関して、どこまで譲歩するのか、しないのか」などというスタンスを定め、知恵をもって備えておく必要があります。
政府には、日本の「国としての目標」を明確にし、戦略を立て、計画に沿って実行する姿勢が求められます。もちろん状況に応じた柔軟な対応も必要ですが、大きな方向性と骨格がなければ、また同じ過ちを繰り返しかねません。
ここでいう「過ち」とは、希望的観測に基づき、十分な戦略を持たず、行き当たりばったりに行動し、苦境に立たされてしまうことです。「未来(=現在)の日本」のために、命をかけ、犠牲になった人たちが、浮かばれるようにしたいものです。
外交・防衛だけでなく、教育や産業政策も含めた「国家としての戦略」を持ち、それを着実に実行していくことが、過去の「反省」を未来に活かす最も重要な道筋ではないでしょうか。