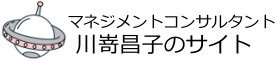不安と希望のメカニズム(上)「失われた時代」からの日本の不安の構造と、それでも希望が生まれる理由

将来に不安を感じている人の割合は?
少し前に、気になった言葉、「不安を希望と夢に変える政治」に関連してブログを書きます。この言葉は、高市早苗さんが自民党の総裁選のときに語ったもので、片山さつきさんも語っていました。
気になったのは、「不安を希望と夢に変える」というからには、あらためて、今の日本で不安を感じる人が多いのか、割合は?というのがひとつ。
もうひとつは、あくまでも私の考えだと「失われた30年」になったのに政治的要因は少なからずあるのを、これから希望や夢に変えられるのかということです。これは決して非難しているわけではなく、もちろん変えて欲しいし、変わる部分はあると思いますが、どこまで変わるのか、変わらないのか、期待半分という感じです。
そこで、不安と希望に関する調査を調べてみました。
まず、2023年にBIGLOBEが18~69歳を対象に行なった「日本社会の未来に希望を感じるか?」という調査。
希望を「感じる・やや感じる」は、各世代で、2~3割。逆に希望を「あまり感じない・感じない」が7~8割となっています。
そして、フォーイットの2023年の「将来の不安」に関する調査でも、8割以上の人が将来に何らかの不安を感じているという結果でした。
また、何に対して不安を感じているのかでは、全部の年代で一番高かったのが「生活費の不安」。次に「健康、医療費の不安」「年金や社会保障の不透明さ」。この3つは、年代別では、50代、60代が高く、性別では女性が高くなっています。
さらに、若い世代では「仕事やキャリアの不確実性」「子供の教育費用の不安」などが入っています。他に「自然災害や緊急事態への不安」も挙がっています。
少なくとも、2023年のこれらの調査では、多くの人が、金銭的に、また、健康や災害にも不安を感じていることが分かります。
日本の国際競争力、半導体シェアは低下したまま
そもそも、これまでの日本は、1990年代から2023年ぐらいまで「失われた30年」といわれる、経済が停滞している状態でした。まあ、今も「失われた時代」を抜け出して「不安」がなくなったとは言えないと思いますが。
日本の国際競争力は、IMD(国際経営開発研究所)の調査では、1989年から1992年まで1位だったのが、徐々に下がってきて、2024年では38位となっています。
高市早苗さんは「Japan is back.」とも言っていますが、これは、日本が、これから国際社会において、再び競争力を取り戻し、強い存在感を示すという表明であり、38位なので、決して、今、戻って来たというわけではありません。
ちなみに半導体に関しても、1986年には世界の半導体出荷シェアで、日本がアメリカを抜き1位、シェア50%でした。
2024年の売上高のシェアでは、1位がアメリカで約6割、2位が中国、3位が韓国、そして、ヨーロッパと日本が4位で、それぞれ6%ぐらいです。
そして、半導体の売上高はアメリカがトップですが、これを生産している生産能力のシェアでは中国が1位、台湾が2位です。
アメリカ企業は、製品を企画、設計して、おもに台湾に生産を依頼していますが、中国も自国分だけでなく、香港を経由して世界に販売したり、韓国、台湾、ベトナムなどにも販売しています。
アメリカ企業のように自社が工場をもたないのを「ファブレス」企業と言い、逆に、他社に依頼されて作るのを「ファウンドリ」企業と言いますが、台湾のTSMCがその「ファウンドリ」企業の代表です。
かつての日本企業は、企画、設計から製造、販売まで一貫して行なっており、これを「IDM」企業というのですが、世界のビジネスモデルは変わっています。
1990年の半導体売上高ランキングで、上位10社のうち6社が日本企業でしたが、今は1社も入っていません。
将来の投資がムダなコストとして削減された結果
「失われた30年」のスタートは、バブル崩壊ですが、その後の政策は、多少の効果があったものもありますが、概ね失敗しています。
デフレ経済が続くなか、政府は「緊縮財政=信頼回復」と捉え、公共事業を削減し、「民間主導での効率的な経営」を目指しました。
企業は「コストカット=経営努力」と捉え、支出を減らし、内部留保を増加させる方向にし、教育や人材育成、人件費、研究開発費を、投資ではなくコストとしてカットしました。
国の「将来にツケを残さない」ための支出削減、消費税増税は、アメリカからの市場開放、規制緩和の圧力も相まって、皮肉なことに、将来を担う若者世代が「就職氷河期」や「非正規雇用」の拡大で苦しみ、国内の需要も失われ、中小企業の倒産や、国民の貧困化につながりました。国はかえって税収減、国の借金が増大する結果となりました。
研究開発などの新しい投資が削られたことで、日本はデジタル化によるイノベーションなどにも遅れが出ています。
このように政府の施策は裏目に出て、経済全体の縮小と国民の苦悩、国際競争力の低下を招くことになりました。
さらに、各地で地震が起き、コロナが発生。
現在も国際的な不安、台湾有事や北朝鮮の核、世界の紛争、難民問題や外国人の移民問題などの不安要素はあります。
つまり、今の社会での「不安」は、単なる個々人の気分ではなく、社会構造の一部として形作られ定着してしまったようにも感じられます。
不安と希望はコインの裏表
しかし、この「失われた30年」のなかにあって、私は、国内で、希望に溢れる環境にいたので、そもそも「不安」と「希望」って何だという、この2つの感情の正体を少し掘り下げてみたいと思います。
まず、「不安」とは何か?
不安は、まだ見えない未来に対して、「どうなるんだろうか?」「大丈夫だろうか?」と警戒する気持ちです。
これは、人間が生き延びるために備えている“アラーム”で、脳が「これから起きるかもしれないリスク」に対して、反応しているわけです。
だから、不安は悪いものではありません。
むしろ、「守りたいものがある」ので不安を感じる。自分や家族の暮らし、仕事、健康、安全を守りたいというサインでもあります。
一方、「希望」とは何か?
希望は、まだ見えない未来に対する期待、「きっとこうなる」「きっとできる」と信じる力です。
不安と希望はひとつのコインの裏表で、守りと攻めのようなものです。
不安が「守りたい心」で、期待は「攻める心」前向きにゲットしていこうという心です。
希望が循環し、加速していた職場
私は20代から40代までベンチャー企業で働き、自社だけでなく、関連企業や顧客企業も急成長しました。そして、私は経営者向けビジネス雑誌の編集長だったので、成功している企業を取材で訪れてもいました。
そうした企業には、ある共通点がありました。
それは「希望が溢れている」ということです。
自社も、取材で訪れた成長企業にも、同じ空気がありました。
経営者は未来の話をするとき、まるで少年少女のように目を輝かせて楽しそうに語ります。そして、面白いこと、ジョークを言って周りの人を笑わせ、本人もよく笑います。
取材している私も笑って、笑いすぎて、翌日顔が痛いぐらいでした。
そういう企業は、社員たちも明るく軽やかに動いています。
エネルギーが溢れている感じなのです。
社員も取引先も、最初から全員がうまくいくことを信じていたわけではありません。
けれども、少しずつみんなの仕事がうまくいき、成果が出てくるうちに、「これはうまくいくんじゃないか」と思え、「自分たちはできるんじゃないか」と信じ始めます。
そうなると、「これもできる」「あれもやってみよう」と前向きな気持ちになります。
困難があっても「なんとかなる」と思えますし、失敗しても「勉強になった。これから本気を出すぞ」などと言って、本人もまわりも笑っています。
そして、頑張ってクリアできると、自信が生まれ、笑顔になります。
“希望の循環”のような状況になり、だんだん「こうしたい」と思った時から、実際に動いて、それを実現させるまでのスピードが速くなっていきます。
あるとき、ある部署で、新人が「将来的に、海外で働きたい」と言ったら、違う部署の人に「海外で働きたいの? だったら、そういう仕事あるけど」と言われ、新人が驚いているうちに、「担当の人に連絡するね」と言われ、担当の人がやってきていました。
ですので、下手に「こうしたい」と言うと「あっ、それ、担当者を探している部署があるよ」とか、「はい、企画書書いて」「予算はいくらで、いくらの売上になるの?」などと言われる状態になっていました。
そして、だんだんそれが自分たちのまわりでは普通の感覚になっていきます。
あの環境では、希望を持つことに特別な努力はいらず、空気のように自然な状態だったのです。
学習性無力感で「頑張っても頑張り損」という気持ちに
しかし、そうした環境を離れて気づきました。
世の中には、実は「希望」があまり溢れていない。
むしろ、日本は「失われた時代」で「どうせ無理だ」「やっても変わらない」という雰囲気に包まれている。
これは、“学習性無力感”という心理状態です。
セリグマンという心理学者の理論で、努力しても報われない状況が続くと、何をしても無駄だと感じて、行動を起こさなくなるという心理状態です。
「不安」は「どうなるんだろう?」という気持ちですが、この「学習性無力感」は「どうにもならない」という気持ちで、不安を通り越しています。
「どうせ言ってもムダ」「頑張っても頑張り損」と、人も組織も無気力になってしまうのです。
“希望の循環”とは逆で、頑張り損なので頑張らない。ちょっと頑張ってもすぐ諦める。続かない。クリアできず「やっぱりな」と思う。自信は失われたまま。上の人に不機嫌になられたり、責められたりもする。笑顔にはならず、本人もネガティブな気持ちになる。「こうしたい」と思わない。思ってもムダと感じる。やはり、頑張り損なので頑張らないと停滞していきます。
しかし、成長企業の人たちにとっても、社会の環境は同じであり、とくに能力が高い人たちが集まっていたわけでもありません。
では、なぜ成長企業の人たちは、そんななかで、希望を見出せたのでしょうか?
答えは簡単です。
それは、彼らが「自分たちの未来を自分たちで創ろうとしていた」からです。
ビジネスを創るというのは、まさに未来を創るということでもあります。
誰かが創ってくれる、良くしてくれるのを待つのではなく、自分たちで創ろう、良くしようとする。
人から「そんなの無理」「甘い」と言われても、「ぜったい創る」と思って動き出す。
それが希望の正体ではないでしょうか?
地方では、「産業と言えるものがない」「大きな企業がなく、よい仕事が少ない」「チャンスがない」と言われがちですが、そういったなかでも、もし、「自分たちの手で未来を創れるのでは」と思えれば、そう動くかもしれません。
とくに今は、インターネットで世界中とつながっている時代なので、昔に比べて、可能性が高くなっているのではないでしょうか?
そういう意味で、“希望のある地域”とは、“未来を創ろうとする人がいる地域”なのかもしれません。
では、どうすれば、「希望」を育てられるのか?
長くなったので、次回、不安と希望の“心のメカニズム”、心理的なことについて書きます。