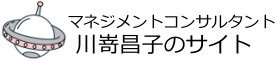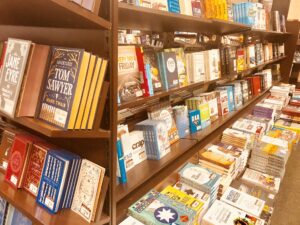ハラスメント調査から見える、これからの職場コミュニケーションの形

ハラスメントに関する調査
拙著「不本意ながらパワハラ認定された上司がホワイト上司になる方法」に、日本インフォメーションの「ハラスメントに関する調査」(2024年)を載せています(紙の本はP44)が、2025年の同調査の結果が出ていました。
ハラスメント意識の高まりで「働きやすくなった」「やや働きやすくなった」人の割合は、昨年が55.8%だったのが、今年は61.4%になり、若い人、女性ほど、その傾向が高くなっています。女性は、どの年代でも「働きやすくなった」人が「働きにくくなった」人の割合を超えていますが、男性は、50代と60代で、「働きにくくなった」人の割合が「働きやすくなった人」の割合を超えていて興味深いです。
同調査では、コミュニケーションの変化についても聞いていますが、職場の人、取引先を問わず、会食や飲み会に「参加すること、誘うこと」が減り、「メールやチャットなど文章でのコミュニケーション」が増えたとなっています。
飲みニケーションに頼らないコミュニケーションを
パワハラの原因として、コミュニケーション不足が言われていますが、上司部下、同僚がお互いにどういう人か、理解し合う機会を増やす必要があると思います。
メールやチャットは便利ですが、Web会議ツールで顔を出したほうが、表情などの非言語情報も増え、さらにリアル(対面)のほうが、空気感、臨場感などの情報も増えるので、バランスが大事でしょう。
そして、かつての「飲みニケーション」すなわち、職場内外での飲み会はコロナで減少し、また、調査(『飲みニケーション』についてどう思うか ネクストレベル 2024年4月)でも、「いらない」「どちらかというといらない」という人が合計64.5%となっています。
「飲みニケーション」に頼らず、むしろ、勤務時間内に、お互いを知り、コミュニケーションが深まる仕組みを作るなり、ワークショップを行なったほうがいいでしょう。
パワハラ対策においては、コミュニケーション、とくに上司から部下への伝え方が大切です。次のブログで、同じことを言うのに、「パワハラ上司」と見なされやすい言い方と「ホワイト上司」の言い方の違いを書きます。