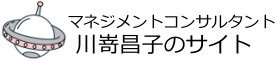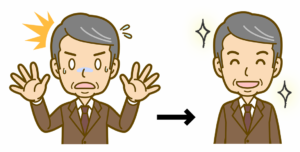「パワハラ上司がホワイト上司に」本で思うこと(2)出版形態は自分にとって新たな挑戦だった

先日出版した「不本意ながらパワハラ認定された上司がホワイト上司になる方法」に関して、前回は、本の中身のことを書きましたが、今回は、出版形態について書きます。
商業出版・セルフ出版・自費出版
これまで私が書いた4冊とその電子版は、出版社から出ています。ネットだけでなく書店で売っている、いわゆる「商業出版」です。
しかし、今回の本(紙、電子)は、Amazonから出している「セルフ出版」です。
KDP(Kindleダイレクト・パブリッシング)、キンドル本、オンデマンド出版などと言われ、いわゆる「自費出版」とは違い、Amazonで出すことにお金はかかりません。
売れたら、手数料が引かれて、入金される仕組みです。
今回の本は、もともと出版社から出す予定で、原稿を書いていたのですが、厳しい感じになり、別に当たってもらっていたのですが、半年経ってしまったので、もう自分で出そうと思ったのです。
セルフ出版に興味はあったのですが、出版社から出せるのなら、そのほうがいいという気持ちもありました。
セルフ出版は意味がない?
セルフ出版に否定的な方は少なくなく、出しても意味がない、下手に出すと出版社では出せなくなるとおっしゃる方もいます。
確かに、商業出版は、編集やデザインなどすべてプロが関わり、ビジネスとして行なっているので、セルフ出版よりレベルが高いのは当然です。全国の書店にも並びますし、販売やマーケティングもプロが行なうので、著者は執筆に注力できます。
しかし、セルフ出版で出したから商業出版が難しくなるということもないでしょう。そもそも何らかの専門家か有名人でもないかぎり、出版社からいきなり「本を出しませんか」と声をかけられることはありません。
セルフ出版は、実際にやってみると、けっこう面白いです。
著者の立場では気付かなかったことで、日々気付くことがあります。
本を作成するまでは思っていたよりも簡単だった
セルフ出版で本を出すまでは、思っていたよりも簡単でした。
本を出すには、原稿を書いて、編集・校正・校閲をし、紙の場合は、表紙や裏表紙、中身(装丁)のデザイン、電子の場合も表紙、その他のデザインをします。
今回、表紙はプロに頼もうと思っていたのですが、プロに頼むためのラフをPhotoshopで作っているうちに、これでいいのではと思えてきました(笑)。装丁も自分でやってみました。
校正は、岩波書店の校正者(フリー時代の師匠)が降臨してきた感じでやってみましたが、後で「こことここ、直して」と言われそうなところを発見しました。でも、まあ、よいかなと。
KDP用の各種設定、登録は、KDPのWebサイトに詳しく書いてあるのですが、文の最後のほうに「日本は未対応」と書いてあったりもします。「e-tax」サイトのように、詳しいが故に迷子になったり、余計なことをしてしまったりしがちです。
しかし、1回やれば分かります。消費税より楽です(自分は簡易課税ではなく、本則課税にしているし……。輸出企業でもないのに)。
電子版はもちろん、紙の本も色校正以外、お金はかかりません。色校正は出さなくてもよいのですが、印刷・製本の実費と送料合わせて、1000円程度なので、出してチェックしたほうがよいでしょう。印刷、製本した見本を送ってくれるので。
一等地の「えっ、ここ?」という場所
出してから、かなりのレッドオーシャンぶりに気づきます(笑)。
KDPは、たとえると、立地は一等地だけれど、エレベーターのない雑居ビルの上の階の「えっ、ここ?」という場所で、一人で喫茶店をやるみたいな感じです。
いろいろ調べていたら、高評価がたくさんついていても、相互系コミュニティ感が高い、情報商材的なものもありました。
そういったなか、あくまでも王道でやっていくために「さて、どうしようか」と、知恵を絞る楽しさはあります。
かつて新規事業立ち上げのサポートをしていたのですが、毎日新たに学ぶことがある、あの感じです。学ぶことが多く、「うわ、しまった、やらかした」とか「ふっふっふ、よしよし」みたいな感じです。
いろいろな事業は、軌道にのって安定してくると、だんだんコスパ、タイパを考え、効率よく回すことに集中し、守りに入ってきますが、0から1への攻めのベンチャー魂のようなものが刺激されて楽しいです。
MKメディアパブリッシングという名前のマイ出版社(笑)を作ったので、そのうちノウハウがたまったら自分以外の本も出せるかもなどと思っています。