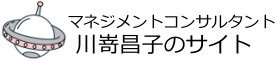表示されない時代の戦い方〜企業編

前回のブログでは、「選ぶ前に表示もされない時代」について書きました。
検索やアルゴリズムが主導する今の時代、どんなに良いサービスやスキルを持っていても、「表示されない」=「存在していない」と同じ扱いを受けてしまう。そんなことが、さまざまな分野で起きています。
その続編として、「表示されない時代の戦い方」というテーマで、2回に分けてお届けします。
今回は「企業編」として、中小企業が抱える「商品・サービスが埋もれる」「求人を出しても応募が来ない」などの課題に対して、「空中戦」と「地上戦」の視点から、どう戦略を立てるかを考えていきます。
土俵にすら上がれていない状態
「良い商品をつくっているのに売れない」「求人を出しても応募がゼロ」
そんな悩みを持つ中小企業は少なくありません。しかし、そんな場合、内容云々以前に、そもそも見つけてもらえていないケースも多いです。
たとえば、Web検索では広告や大手企業が上位を占め、自社のページは埋もれてしまう。SNSで発信しても、フォロワー数や拡散力が弱く、届かない。求人も条件検索で埋もれ、候補者の目にすら触れない —— そんなことが起きています。
つまり、土俵にすら上がれていない状態です。
発見してもらう「空中戦」は難しい
「空中戦」と「地上戦」は、もともと軍事用語ですが、マーケティングなどのビジネス関連でもよく使われます。
「空中戦」は、広告、SNS、検索エンジン対策(SEO)、プレスリリースなどを通じて、不特定多数に知ってもらうための戦略です。広く発信して、見込み客や求職者に“発見してもらう”ための活動です。
中小企業にとって、空中戦は以下の理由で不利になりがちです。
・広告費をかけられない。効果的な広告を出すのも難しい
・SEOやSNS対策の方法が分からない。また、対策に時間やお金をかけられない
・情報発信の際、他社と似たような言葉・写真で、差別化できない
その結果、せっかくWebやSNSで情報発信しても、埋もれてしまう。とはいえ、空中戦は大事なので続けつつ、「地上戦」に力を入れ、そこで得たものを空中戦でも活かす方法にするのがよいと思います。
顔が見える距離で届ける「地上戦」
「地上戦」とは、一人ひとりに直接アプローチし、信頼や共感を築いていく方法。たとえば下記のような活動です。
・既存顧客に紹介キャンペーンを実施
・地域の商工会、交流会、展示会などに参加
・少人数向けのセミナーや説明会を開催
・採用なら、ハローワークや地元の学校と連携し、個別相談を増やす
手間はかかりますが、確実に届くという意味では、地上戦のほうが成果につながることが多いです。また、以前はこのような地上戦をやっていたが、だんだんやらなくなっている傾向もあります。
しかし、空中戦で見つけてもらうのを待つだけでなく、地上戦でこちらから“見つけに行く”戦略をとり、まずは地上戦で“確実な一人”に伝えてみてください。
「誰に何を届けるか」を意識すると言葉が変わる
そして、空中戦でも地上戦でも、「誰に何を届けたいのか」が曖昧だと、発信の言葉がぼやけます。下記を意識してみてください。
・商品やサービスが“誰の、どんな悩みを、どのように”解決するのか
・求人では“どんな人に向いていて、何を提供できるのか”
何でも出来ますより、「〇〇に特化しています」「〇〇が得意です」とジャンルや対象を絞ることで、埋もれず浮き上がってきます。
たとえば、「40代以上のこういう女性を対象にしたサービスで、こういうこだわりがあります。こういうところが評価されています」などです。
なるべく他にはない「オリジナリティ」「メリット」を、あらゆる角度から探ったうえで、いちばん刺さりそうなものに絞って強調したほうがよいでしょう。
こうした視点が明確になると、「言葉の切れ味」が変わります。
そして、その言葉が、空中戦での“引っかかり”を生み、地上戦では“納得”を生みます。
ところで、空中戦と地上戦の両方に力を入れている代表例があります。それは「選挙活動」です。
近年はSNSやYouTubeなどでの発信(空中戦)が目立っていますが、候補者自身が街頭に立ち、握手をし、地元の声に耳を傾けるといった地上戦は、今なお、下記の理由などから大きな影響力を持っています。
・SNSだけでは届かない人がいる。
・検索やアルゴリズムでは動かない心がある。
それは、企業活動にも通じます。
実際に会って話す・関係を築く地上戦の力を、今こそ見直すべき時代かもしれません。
次回は「個人編」として、就活や婚活で「見つけてもらえない」「検索条件で足切りされてしまう」といった悩みに、どのように向き合えばよいかについて考えていきます。