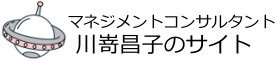日記を書くことの意味――古賀史健著『さみしい夜にはペンを持て』を読んで
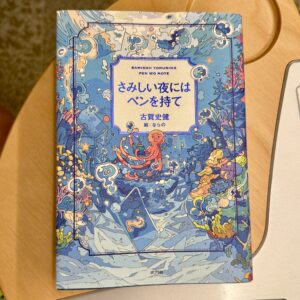
どんな本か調べずに読んだ結果
ツナグバサンカクの金子さんが貸してくれた本。昨日、博多への往復で読みました。
舞台は、海の中の町。主人公は、自己肯定感の低い中学生のタコ、その名も「タコジロー」です。
タコジローは、学校での出来事をきっかけに、学校のバス停で降りられずに終点の市民公園まで行ってしまいます。
そこで出会ったヤドカリのおじさんとの対話を通じて、「話すこと」と「書くこと」の違い、日記を書くことの意味について学んでいきます。
タコジローは、私とは違うタイプなので、共感はしないのですが、著者の発想に興味を持ちました。読み終えて調べてみると、著者の古賀史健氏は、ベストセラー『嫌われる勇気』の共著者でした。文章入門、文章講義などの本も出しています。
この本は、心理学や文章執筆に関する内容を、寓話で書いた本だったのです。
自分には「日報」のほうが書きやすい
この本のテーマは「日記を書くこと」です。「日記」は、その日の出来事やそのときの自分の気持ちを書くもの。
それに対して、自分は「日報」、つまり事実や数値をもとに、分析や対策を書くほうが簡単です。
自分の内面よりも外側、社会や歴史、人の行動心理に関心が向いている割合が高いので、日記よりも日報のほうが書きやすいのかもしれません。
この本では、タコジローが、実際に日記を書くことにより、いろいろなことに気がつきます。ネガティブに捉えていた自分の特徴が、逆に強みになる体験もし、自分のことを好きになります。
日記を書くことが、自分を肯定し、自分を応援する練習になっていたのです。
相手に勝つことが話すことの目的になっている人も
一方で、この本のなかには、「言葉の暴力」も出てきます。
傷つく言葉を使って、スマッシュを打ち込んで、一発で相手を黙らせようとする。
あるいは、話すことが、相手に伝えることではなく、相手に「勝つこと」になっている。自分の非を認めず、よくわからない理屈を並べ、言い負かそうとするウツボリくんの話を読んで、そういう政治家がいるなあと思いました。
また、日記でも、感情を書き殴ると、誰かを責めたり、自分を責めたりする「暴力の言葉」に近くなることが書かれています。
これは、アンガーマネジメント的にも「怒りの発散は炎を燃やすのか、消すのか?」という論文で、「消す」という説(カタルシス理論)は証明されませんでした(→ ブログ)。
ーー
話すことと書くことの違い、書くことも、チャット、感想文、日記の違いなど、いろいろ考えさせられる本です。